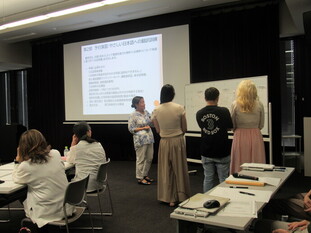災害時のやさしい日本語講座(2025年9月9日)を開催しました
地域に暮らす外国人住民に、伝える! 伝わる! 災害時のやさしい日本語講座
大阪北部地震などの事例紹介とワークショップ
9月9日(火曜日)午後に市役所本庁舎 2階 大会議室で「災害時のやさしい日本語講座」を開催しました。防災士や日本語学習支援者を含む市民の方々、市職員など約20人が参加しました。
第一部 大阪北部地震などの事例紹介とやさしい日本語のつくり方
前半の講義では、講師の岩城あすかさんから、(公財)箕面市国際交流協会の活動紹介、学生時代に体験したトルコでの地震や7年前の大阪北部地震について、そしてやさしい日本語のつくり方についての話をしていただきました。
講義の初めに、アイスブレイクとして簡単なゲームをしました。参加者の背中に色のついた丸いシールを1枚貼り、言葉を使わずに同じ色の者同士で集まるというゲームでした。参加者の皆さんは自分の背中のシールの色がわからないため、ジェスチャーを使って集まったり離れたりを繰り返していました。
参加者からは「最後まで一人ぼっちで寂しかった」「同じ色だと思っていたグループから追い出されてショックだった」との感想がありました。実はこのゲームは、避難所での外国人の不安な気持ちを感じてもらうためのゲームでした。
大阪北部地震では「断水」「余震」といった聞きなれない災害用語や「安全を確保してください」といったテレビのあいまいな指示によって、混乱しパニックになっている外国人の姿がみられたそうです。
また、地震の揺れによりガスの供給が自動で遮断された後、自分でガスメーターのボタンを押して復旧できる方法があったものの情報が得られなかった、あるいはガスメーターがどこにあるのかわからなかったので復旧するのに時間がかかった、といったトラブルが多数あったようです。
地震についての基礎知識のなさが、より一層不安を増幅させてしまうことや、日本語や日本に詳しい知人の有無によって災害時の行動に違いが出たことがわかりました。
やさしい日本語のつくり方については、具体的に表現する、使役や受け身表現は避ける、日付は年月日で表すなど注意する点について学びました。そして、やさしい日本語に正解はなく、相手の状況によって表現を変えることや、より多くの人にわかることを目指すことも大切だと教わりました。


第二部 やさしい日本語への翻訳訓練(ワークショップ)
後半のワークショップでは、4グループに分かれてグループワークをしました。
洪水を想定した災害時における市役所からのお知らせを、短い時間でやさしい日本語へ翻訳するという演習に挑戦しました。
「り災証明書の交付」「申請に必要なもの」「本人確認書類」「受付・発行窓口」「提出方法」などについて書かれたお知らせの内容を、まずは1人でやさしい日本語に翻訳した後、グループで話し合ってA3用紙にまとめ、出来上がったものをホワイトボードに貼り出しました。
その後、ゲストの3人の外国人住民の方々に、各々一番わかりやすい貼り紙を選んでもらいました。選んだ理由を尋ねると、言葉が少なくて読みやすい、漢字表記が少ない、漢字にはルビが振ってある、持っていくものやどこに持っていけばいいのかがすぐにわかる、といった点をあげていました。
普段から日本語学習支援をしている方からも、やさしい日本語に直すのは難しいといった感想や、やさしい日本語に翻訳する際には文を削るだけでなくつけ加える方法もあると聞いて驚いた、という声がありました。
外国人にとって、自分の国の言葉で書いてある情報がやはり一番わかりやすいですが、やさしい日本語を使うことによって、短い時間で正確に情報を伝えることが可能になります。やさしい日本語の重要性をさらに感じました。
豊岡市では、今後もこのような研修を行っていく予定です。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
くらし創造部 多様性推進・ジェンダーギャップ対策課 人権・多文化共生係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-0341 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。