マダニの感染症「重症熱性血小板減少症候群」に注意しましょう
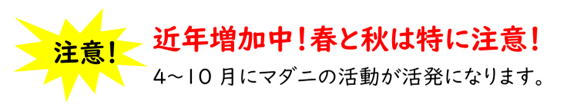
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)とは
SFTSウイルスを持つマダニにかまれることで感染する病気です(ウイルスを持つマダニは数パーセント)。
マダニは森林や草むらにいます
マダニは、3~8ミリと比較的大型で硬い外皮に覆われ、森林や草むらに生息しています。衣類や寝具、食品など屋内に発生する家ダニ(0.5ミリ)とは異なります。
マダニにかまれてから6日~2週間程度の潜伏期間を経て、発熱、消化器症状(食欲低下、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛)などの症状がでます。重症になると死亡することもあります。
その他にもマダニにかまれたことで感染する病気は、日本紅斑熱、ライム病、ツツガムシ(ダニの一種)によるツツガムシ病があります。

注:右上下 タカサゴキララマダニ(厚生労働省ホームページから)
感染の予防には長袖、長ズボンで肌を覆う

森林や草むら、やぶ、畑などに入るときには、長袖、長ズボン(シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる)足を完全に覆う靴(サンダルなどは避ける) 、帽子、手袋を着用し、首にタオルを巻くなど肌の露出を少なくすることが大事です。
- 服は明るい色のもの(マダニを目視で確認しやすい)や化学繊維素材(マダニがつきにくい)がお薦めです。
- 市販の防虫スプレーは、使用方法をよく読み、使用しましょう。
活動のあとは
屋外活動後はすぐに入浴し、脇の下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭部(髪の毛の中)などマダニにかまれていないか確認してください。
マダニにかまれたらどうすればよい?
- マダニにかまれても痛みがなく気が付かない場合が多いとされています。
- 人や動物に取りつくと皮膚にしっかりと口器を突き刺し、長時間(数日~10日間以上)吸血します。
- 吸血中のマダニに気が付いた際、無理に引き抜こうとすると、マダニの一部が皮膚内に残って化膿したり、マダニの体液が逆流する恐れがあるので、医療機関で処置(マダニの除去、洗浄など)をしてもらってください。
- すぐに受診できない場合はワセリン法をお試しください。
ワセリン法
- 無理に取り除こうとせず、たっぷりのワセリンで、かまれたところをマダニの体ごと覆います。
- そのまま30分ほど放置するとマダニが窒息します。
- ガーゼで拭き取ります。
注: マダニにかまれた後、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱、食欲低下、嘔吐、下痢などの症状があったときには医療機関で診察を受けてください。
-
兵庫県 啓発用リーフレット1「マダニに注意!」 (PDF 590.3KB)

-
兵庫県 啓発用リーフレット2「そのマダニウイルスもっているかも?」 (PDF 2.9MB)

-
「ダニ」にご注意ください(厚生労働省) (PDF 777.3KB)

-
マダニ対策、今できること(厚生労働省) (PDF 4.3MB)

問い合わせ・相談窓口
豊岡市 健康増進課
電話:0796-24-1127
豊岡健康福祉事務所 健康管理課
電話:0796-26-3660
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-1127 ファクス:0796-24-9605
問合せは専用フォームを利用してください。
