RSウイルス感染症に気をつけましょう
RSウイルス感染症とは
RSウイルスの感染による呼吸器の感染症です。生後1歳までに半数が、2歳までにほぼ100パーセントの子どもが一度は感染するとされています。RSウイルスは、一般的に乳幼児の呼吸器感染症の原因ウイルスとして知られていますが、高齢者や基礎疾患のある成人においても肺炎などを引き起こすことがあります。生涯にわたり、感染を繰り返しますが、特に乳幼児の初めての感染や、高齢者、持病のある人などは重症化することがあるので注意が必要です。
RSウイルス感染症は、近年は夏から増加傾向となり、秋にピークが見られていました。しかし、2021年以降は春から初夏に継続した増加がみられ、夏にピークが見られています。感染力が強く、家庭内感染を起こすことがあるため、感染予防に努めましょう。
症状
潜伏期間は2~8日で、発熱、鼻汁などの症状が数日続きます。多くは軽症で自然軽快しますが、重症化すると咳がひどくなる、喘鳴(ヒューヒュー、ゼーゼーという音)が出る、呼吸困難となるなどの症状が出現し、場合によっては細気管支炎、肺炎などを起こします。
呼吸が苦しそう、食事や水分摂取ができないときは医療機関を受診しましょう。
重症化しやすい人
- 基礎疾患を有する小児(特に早産時や生後24カ月以下で心臓や肺に基礎疾患がある小児、神経・筋疾患やあるいは免疫不全の基礎疾患を有する小児など)
- 慢性呼吸器疾患などの基礎疾患を有する高齢者
感染経路
RSウイルスは、主に接触感染と飛沫感染で感染が拡がります。
- 接触感染
感染者との直接の接触や、感染者が触れたことによりウイルスがついた手指や物品(ドアノブ、手すり、スイッチ、机、いす、おもちゃ、コップなど)を触ったり、なめることで感染すること - 飛沫感染
感染者が咳やくしゃみ、会話の際に口から飛び散るしぶきを浴びて吸い込むことにより感染すること
感染を拡げないために
一般的な感染予防対策としては、手洗い、手指のアルコール消毒、マスクの着用を含む咳エチケットが大切です。
手洗いによる手指衛生
RSウイルスは、接触感染によりうつりやすいため、ウイルスの体内への侵入を防ぐため、手洗いが有効です。
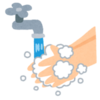
RSウイルスには、アルコール製剤による手指衛生も有効です。
咳エチケット
RSウイルスは、軽い風邪症状で済むことが多いため、RSウイルスに感染していることに気づかないまま周囲の人にうつしてしまうこともあります。周囲の人への感染を防ぐため、必要に応じてマスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。発熱、鼻汁、咳などの症状がある場合、可能な限り乳幼児との接触を避けることが乳幼児の発症予防につながります。
ドアノブやおもちゃのこまめな消毒
子どもたちが日常的に触れるおもちゃ、手すりなどはこまめにアルコールや塩素系の消毒剤などで消毒しましょう。
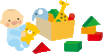
感染に関する情報
RSウイルス感染症の流行情報について知り、日頃から予防対策を心がけましょう。
下部のリンクから、豊岡健康福祉事務所管内(豊岡市・香美町・新温泉町)の感染症の最新情報を確認することができます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-1127 ファクス:0796-24-9605
問合せは専用フォームを利用してください。
